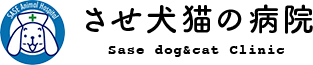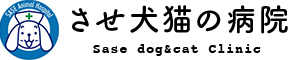「急に動かなくなった」「足を引きずっている」——愛犬にこんな症状が現れたら、どうしたらいいのか不安になりますよね。その原因として考えられるのが、「椎間板ヘルニア」という病気です。
椎間板ヘルニアは、放置すると麻痺や歩けなくなるといった深刻な状態に進行することがありますが、適切な診断や治療を受ければ、症状が改善し回復が期待できるケースも多く報告されています。
今回は、椎間板ヘルニアの特徴や症状、そして緊急時の対応について解説します。

■目次
1.椎間板ヘルニアとは?
2.椎間板ヘルニアの緊急性を判断するポイント
3.椎間板ヘルニア発症時から病院へ向かうまでの対応
4.診断方法
5.治療方法
6.手術後のケア
7.再発予防のポイント
8.まとめ
椎間板ヘルニアとは?
犬の背骨(脊椎)は、小さな骨(椎骨)が連なってできています。
椎骨同士の間には「椎間板」と呼ばれるクッションのような構造があり、この椎間板が背骨にかかる衝撃を和らげ、柔軟に動けるよう支えています。
椎間板は、外側の硬い「線維輪」と内側の柔らかい「髄核」でできており、この構造が背骨の安定性としなやかさを保つ役割を果たしています。
椎間板ヘルニアは、この椎間板の髄核が線維輪を突き破り、脊髄を圧迫することで発生します。脊髄が圧迫されると神経に影響を及ぼし、激しい痛みや麻痺といった症状が現れます。
特に椎間板が変性している場合や、ジャンプや急な動きで背骨に強い負担がかかると、発症しやすくなります。
また、椎間板ヘルニアは特定の犬種に多く見られます。特にダックスフンドやコーギー、ビーグルといった胴長短足の犬種は、生まれつき椎間板が変性しやすい体質を持ち、4〜7歳頃に発症することが多いです。
ただし、他の犬種や高齢の犬でも加齢により椎間板が変性し、発症する可能性があります。
椎間板ヘルニアの緊急性を判断するポイント
椎間板ヘルニアの症状は軽いものから重いものまでさまざまです。症状が進行すると治療が難しくなり、回復にも時間がかかるため、早期の対応が重要です。
愛犬に以下のような症状が見られた場合は、状態に応じてすぐに動物病院を受診しましょう。
・軽度:足を引きずる、動きたがらない、散歩を嫌がる
・中度:歩行が不安定、後ろ足がふらつく
・重度:歩けなくなる、後ろ足が麻痺、尿や便の失禁
・緊急状態:激しい痛みで動けない、後ろ足の完全麻痺
そして、以下の症状が見られた場合は、緊急性が非常に高い状態です。時間を置かず、すぐに動物病院を受診してください。
・歩けない、または立ち上がれない
・激しい痛みで鳴き続ける
・尿や便を漏らしてしまう(失禁)
・足を引きずりながら歩いている
・背中に触ると嫌がる、または強く反応する
椎間板ヘルニア発症時から病院へ向かうまでの対応
愛犬が突然歩けなくなったり、痛みで鳴き続けるような様子が見られたりしたら、まずは落ち着いて適切に対応することが大切です。
<発症時の応急処置>
・無理に動かさない
愛犬を無理に動かしたり抱き上げたりすると、背骨に余計な負担がかかり、症状が悪化する可能性があります。愛犬が楽な体勢でいられるよう、静かに見守りましょう。
・縦抱きは避ける
縦に抱っこすると背骨に負担がかかるため避けてください。どうしても抱き上げる必要がある場合は、体全体を支え、水平の状態を保つよう注意してください。
<病院への搬送時の注意点>
動物病院に向かう際は、以下の点に気をつけましょう。
・体が揺れないように固定する
愛犬が動けない場合は、キャリーバッグや箱に入れて、タオルやクッションで体を安定させます。これにより体が揺れるのを防ぎ、背骨への負担を軽減できます。
・事前に病院へ連絡する
動物病院に電話をして、愛犬の状態を詳しく伝えましょう。到着時の対応や緊急処置が必要な場合に備えておくことで、スムーズに診察を受けられます。
診断方法
椎間板ヘルニアが疑われる場合、動物病院では段階を踏んで慎重に診断が行われます。
まずは、飼い主様から発症時の状況や症状の経過について詳しくお聞きします。愛犬がどのような動きや症状を見せたかを正確に伝えることが、診断の手がかりになります。
その後、身体検査と神経学的検査を通じて、背骨や神経の状態を詳しく調べます。神経学的検査では、次のような点に注目して診断が進められます。
・どの神経が影響を受けているか
・足の反射や痛覚の有無
・歩行や姿勢の異常
そして、椎間板ヘルニアの確定診断を行うためには、以下の画像検査が欠かせません。
・レントゲン検査
骨の形状や隙間の異常、骨折の有無を確認します。ただし、椎間板や神経組織の詳細な状態までは把握できないため、補助的な検査として使用されます。
・CT、MRI検査
椎間板や脊髄を立体的に捉えることができ、ヘルニアの正確な位置や神経への圧迫の程度を診断できます。重症度が高い場合や外科的治療が必要なケースでは、特に重要です。
これらの検査結果をもとに、椎間板ヘルニアの重症度が評価され、その後の治療方針が決定されます。
館林市や佐野市にお住まいの飼い主様からも多くご来院いただいている当院では、CTやMRIを用いた精密な診断を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
治療方法
椎間板ヘルニアの治療は、症状の重さや進行状況に応じて「内科的治療」と「外科的治療」のいずれか、または組み合わせで行われます。
<内科的治療>
軽度から中程度の症状では、内科的治療が一般的です。この治療法は、痛みを和らげながら自然治癒を促すことを目的としています。
・鎮痛剤や抗炎症剤の投与:痛みを緩和し、炎症を抑えることで症状を軽減します。
・安静療法:ケージレストなどを利用して愛犬の動きを制限し、椎間板や脊髄への負担を減らします。この期間中、愛犬が過度に動かないよう細心の注意が必要です。
<外科的治療>
麻痺や失禁などの神経症状が重い場合や、内科的治療を続けても改善が見られない場合、さらに症状が急速に悪化している場合には、外科的治療が推奨されます。
手術では、脊髄を圧迫している椎間板の一部を取り除き、神経への負担を軽減します。この処置により、症状の悪化を防ぐと同時に回復の可能性を高めることが期待されます。
椎間板ヘルニアの治療、特に外科的治療には高度な専門知識と技術が必要です。整形外科や神経外科の専門知識を持つ獣医師が治療を担当することで、手術の成功率が上がり、回復の見込みも高まります。
また、最新の医療機器が整った動物病院で診察を受けることで、診断の精度が向上し、愛犬に適した治療計画を立てることができます。
治療法を選ぶ際に迷った場合は、獣医師に詳しく相談し、愛犬の状態や治療の選択肢について十分に理解した上で、飼い主様と愛犬にとって最適な方法を選ぶことが大切です。
手術後のケア
椎間板ヘルニアの手術後、愛犬が回復するには数週間から数か月が必要です。術後1週間ほどは入院し、痛みの管理や傷の状態を確認します。
その後、自宅での療養に移りますが、この時期に無理をさせると再発や合併症のリスクが高まるため、丁寧なケアが重要です。
<術後のリハビリテーション>
手術後、一時的に麻痺や歩行困難が残ることがありますが、適切なリハビリテーションにより回復を目指せるケースが多くあります。
手術後数日以内からリハビリを始めるのが理想的で、早い段階で筋力を取り戻すことが回復の鍵です。
主なリハビリテーションの方法には、以下のようなものがあります。
・水中療法
水の浮力を利用して体への負担を軽減しながら筋力を鍛えます。泳ぎや水中歩行が含まれます。
・軽い散歩
最初は短い距離から始め、愛犬の様子を見ながら徐々に運動量を増やします。
・マッサージ
血流を促進し、筋肉の硬直を防ぐため、優しくマッサージを行います。
・ストレッチ
獣医師やリハビリ専門家の指導を受けながら、軽いストレッチを行います。無理のない範囲で行うことが重要です。
<自宅でのケアポイント>
術後の回復を順調に進めるためには、自宅での環境作りと細やかな管理が欠かせません。
・安静を保つ環境作り
ケージやサークルを活用し、無理なく静かに過ごせる環境を整えます。
・滑りにくい床材の使用
フローリングなど滑りやすい場所では、滑り止めマットやカーペットを敷き、転倒や無理な動きを防ぎます。
・傷口のチェック
毎日、傷口の状態を確認します。赤みや腫れ、異常な分泌物が見られる場合は、すぐに動物病院に連絡してください。
・食事と体重管理
術後は運動量が減るため、食事量を調整して体重増加を防ぎます。体重が増えると背骨への負担が大きくなり、再発リスクが高まるため注意が必要です。
再発予防のポイント
椎間板ヘルニアを再発させないためには、日常生活における環境づくりと適切なケアが欠かせません。
まず、高い場所への昇り降りは背骨に負担をかけるため、避ける工夫をしましょう。階段やソファにはスロープを設置し、愛犬が無理なジャンプをしなくても移動できるようにすると安心です。また、急激な動きや激しい運動も控えるようにしましょう。
次に、体重管理も忘れてはいけません。
体重が増えると背骨への負担が大きくなり、再発リスクが高まります。理想体重を維持するために、定期的に体重を測り、獣医師と相談しながら適切な食事量や運動量を調整しましょう。軽い散歩や適度な運動は、健康を維持するうえで効果的です。
また、間食を控え、栄養バランスの良い食事を心がけることも重要です。
椎間板ヘルニアは再発の可能性がある病気です。定期的に動物病院で検診を受け、椎間板や神経の状態をチェックしてもらいましょう。異常が早期に発見されれば、再発を未然に防ぐことができます。
まとめ
椎間板ヘルニアは、愛犬の生活に大きな影響を及ぼす可能性がありますが、早期発見と適切な治療を行えば、多くの場合で改善が期待できます。
手術後はリハビリや日々のケアを丁寧に続け、愛犬が再び元気に動ける日を目指しましょう。
再発を防ぐためには、適切な運動量や体重管理が欠かせません。さらに、定期的な健康診断で椎間板や神経の状態を確認し、異常があれば早期に対応することが大切です。
日々のケアをしっかり行いながら、愛犬が安心して楽しく過ごせる環境を整え、健やかな毎日をサポートしていきましょう。
■歩き方に関わる病気はこちらでも解説しています
・犬の橈尺骨骨折について┃小型犬に多い前足の骨折
・犬の前十字靭帯断裂について┃大型犬によくみられる膝の病気
・犬の股関節脱臼について┃関節に強い外力が加わった時に脱臼する
・歩き方の変化は関節炎のサイン?|初期症状を見逃さず健康な生活をサポート
栃木県佐野市にある犬、猫専門動物病院
させ犬猫の病院